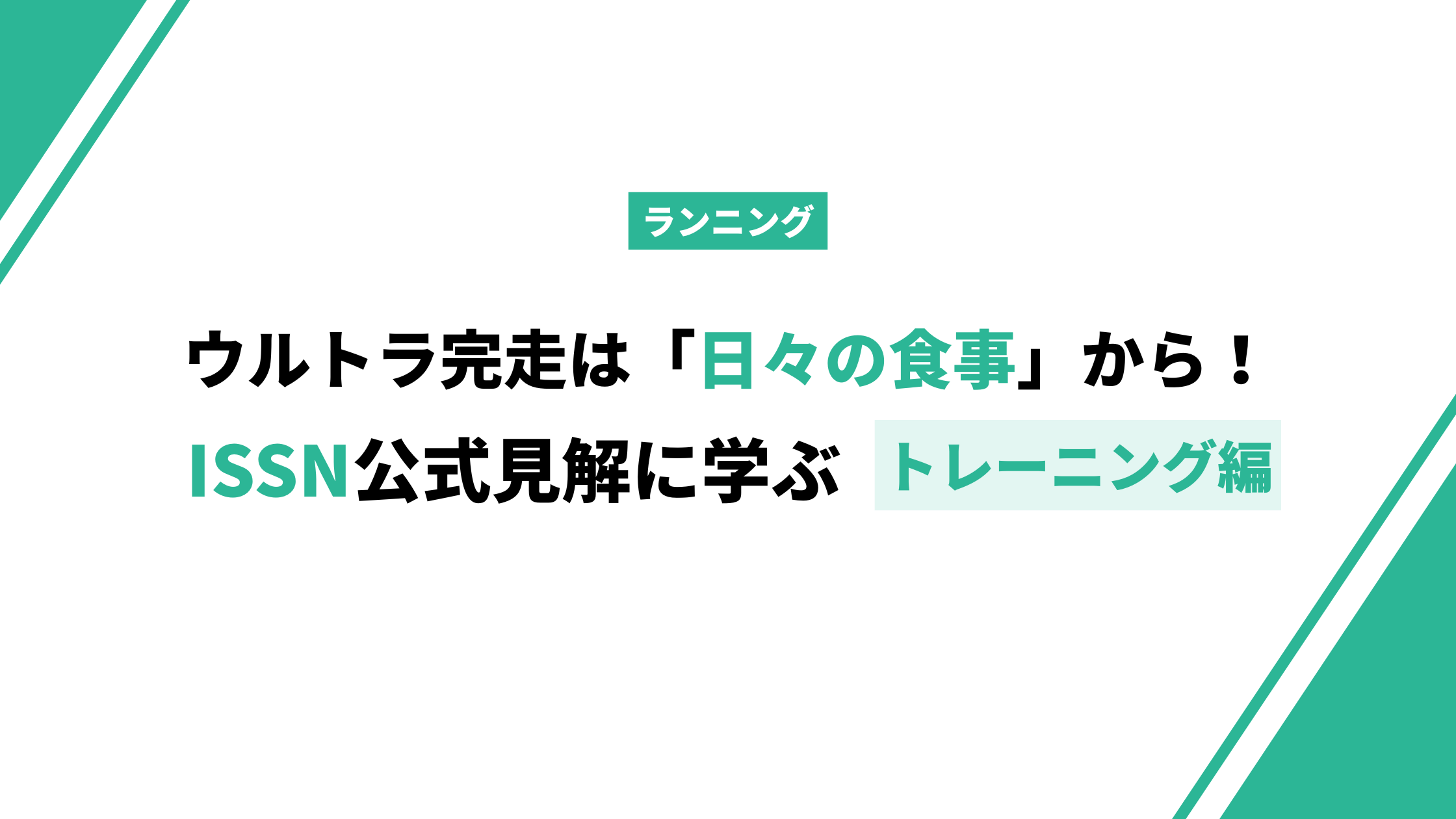100kmウルトラマラソンを完走するためには,レース当日の補給戦略(エナジージェルや水分補給)が注目されがちです。しかし,レース本番でどれだけ完璧な補給を計画しても,それを受け止める「身体」ができていなければ,100kmという長い距離を走り切ることはできません。
その「身体の土台」を作るのが,レースに至るまでの数ヶ月間にわたる日々のトレーニング期の食事です。
この記事では,スポーツ栄養学の世界的権威である国際スポーツ栄養学会(ISSN: International Society of Sports Nutrition)が公式に発表した「ウルトラマラソンに関するポジションステートメント(nutritional considerations for single-stage ultra-marathon training and racing)」に基づき,完走できる身体を作るための「トレーニング期の栄養戦略」を解説します。
なお,ウルトラマラソンを走る管理栄養士である筆者が,このポジションステートメントの実践のために普段から行っている事項についても盛りこみます。
この記事を読めば,科学的根拠に基づいた「強い身体」の作り方がわかります。トレーニングの効果を最大限に高めるための食事法を学びましょう。(なお,レース当日の具体的な補給方法については,次回の【レース編】で詳しく解説します。)
必要なエネルギー・栄養素量
エネルギー
ウルトラマラソンのトレーニング期間中は,走る距離・時間が長くなりますので,それに伴って必要なエネルギー(カロリー)量も増加します。
まずは体重とトレーニング時間(距離)から,必要なエネルギー量の目安を把握しましょう。下記は,時速8.4kmのペースで走った場合の目安です。
- 1時間走る場合:35~40kcal/体重kg程度
- 3時間走る場合:50~55kcal/体重kg程度
より詳細な目安は,以下の表を参考にしてください。
| 性別 | 体重 | 体脂肪率 | 運動時間 | 総エネルギー (kcal) | 体重あたり (kcal/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 50kg | 15% | 1時間 | 2,004 | 40.1 |
| 3時間 | 2,726 | 54.5 | |||
| 70kg | 24% | 1時間 | 2,443 | 34.9 | |
| 3時間 | 3,455 | 49.4 | |||
| 男性 | 65kg | 10% | 1時間 | 2,553 | 39.3 |
| 3時間 | 3,492 | 53.7 | |||
| 85kg | 20% | 1時間 | 2,959 | 34.8 | |
| 3時間 | 4,187 | 49.3 |
上記をベースに,走った距離が長い(時間が長い・ペースが速い)場合は,追加された1kmあたり体重1kgあたり1kcalを追加するのが目安となります。例えば,女性,体重50kgの人が時速8.4kmではなく10.4kmで走った場合は,追加された2km×体重50kgで100kcalを追加し,2,104kcalが目安となります。
筆者の場合は,毎日の体重測定に加え,摂取エネルギー・消費エネルギーを計算して調整しています。摂取エネルギーは,アプリの「あすけん」の有料版で確認しています。私の場合は,上記の目安でエネルギー摂取をすると太り気味になるため(省エネ体質なのか?),少し控えめで調整しています。日々の体重と摂取・消費エネルギーをモニタリングして自分に合った量を見つけるのが重要だと思います。
炭水化物
上記の必要とされるエネルギー量の60%を炭水化物から摂取することが推奨されます。これを体重あたりに換算すると,以下の量が目安となります。
- 1時間走る場合:約5~6g/kg体重
- 3時間走る場合:約7~8g/kg体重
例えば,必要なエネルギー量が2,004kcalであった場合,2,004kcal×60%で約1,200kcalを炭水化物から摂取します。炭水化物からは1kcalあたり4kcalのエネルギーを得られますので,約300gの炭水化物が必要です。
ただし,トレーニングの負荷が非常に大きい場合(例:高強度のインターバル走や,3時間を超えるロング走)には,7〜10g/kg体重の炭水化物が必要になるケースもあります。
【参考】体重・性別・運動時間別の炭水化物必要量(総エネルギーの60%として計算)
| 性別 | 体重 | 運動時間 | 炭水化物量 (g) | 体重あたり (g/kg) |
|---|---|---|---|---|
| 女性 | 50kg | 1時間 | 301 | 6.0 |
| 3時間 | 409 | 8.2 | ||
| 70kg | 1時間 | 366 | 5.2 | |
| 3時間 | 518 | 7.4 | ||
| 男性 | 65kg | 1時間 | 383 | 5.9 |
| 3時間 | 524 | 8.1 | ||
| 85kg | 1時間 | 444 | 5.2 | |
| 3時間 | 628 | 7.4 |
また,エネルギー同様に,これをベースとして,走った距離が長い(時間が長い・ペースが速い)場合は適宜追加していく形となります。エネルギーは,追加された1kmあたり体重1kgあたり1kcalを追加でした。炭水化物比率を60%と考えると,0.6kcalつまり0.15g/kg体重/kmの炭水化物が必要という計算です。例えば,女性,体重50kgの人が時速8.4kmではなく10.4kmで走った場合は,追加された2km×体重50kg×0.15gの炭水化物ですので,追加で15gの炭水化物が必要になるというのが目安となります。
筆者の場合は,これだけの量を通常の食事だけで摂取するのは大変なので,炭水化物サプリメント(マルトデキストリン)を使っています。プロテインサプリメントに混ぜて使用することが多いです。また食事で摂る場合でも,お米(ご飯)が体質に合っているように感じるので,可能な限りお米で摂取するようにしています。
たんぱく質
このポジションステートメントでは,下記のように記載しています:
- 1.6g/kg体重を超えるたんぱく質摂取を推奨
- より多くのエネルギーを必要とする場合には2.5g/kg体重まで正当化される
なお,「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では,成人のたんぱく質摂取の目標量として,エネルギーの13~20%を設定しています。その範囲で,最初に示したエネルギー必要量で計算してみると下記のようになります。
| 性別 | 体重 | 運動時間 | 総エネルギー (kcal) | たんぱく質摂取量 (g) (13-20%) | 体重あたり (g/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 50kg | 1時間 | 2,004 | 65-100 | 1.3-2.0 |
| 3時間 | 2,726 | 89-136 | 1.8-2.7 | ||
| 70kg | 1時間 | 2,443 | 79-122 | 1.1-1.7 | |
| 3時間 | 3,455 | 112-173 | 1.6-2.5 | ||
| 男性 | 65kg | 1時間 | 2,553 | 83-128 | 1.3-2.0 |
| 3時間 | 3,492 | 113-175 | 1.7-2.7 | ||
| 85kg | 1時間 | 2,959 | 96-148 | 1.1-1.7 | |
| 3時間 | 4,187 | 136-209 | 1.6-2.5 |
これを見てみると,13%では1.5g/kg体重に届かないケースがありそうですが,範囲から大きくは外れていなさそうです。必要エネルギーが多い場合では20%まで摂取してしまうと2.5g/kg体重を超えるケースもありますが,大きくは超えませんし上限の目安としては機能するかと思います。
筆者の場合は,体重が約60kgなので90gは最低限摂取するようにしています。昼食と夕食で30gずつ,朝食は主にプロテインサプリメントを活用しています。また,週末にロング走を行う場合は,食事に加えて運動の前後にもプロテインサプリメントを摂取することで,必要量の増加に対応しています。
エネルギー効率を最大化するトレーニング戦略
ウルトラマラソンランナーのトレーニングで重要なのは,脂肪を使える能力を高めることです。ウルトラマラソンでは体に蓄えた炭水化物のみで走りきるのは難しく,体内の脂肪を効率的に使う必要があります。この目標達成に向け,炭水化物摂取を調整する方法が提唱されています。
運動前の炭水化物(CHO)摂取の回避
トレーニング開始90分以内の高炭水化物食品,特に高グリセミック(GI)食品の摂取を避けることが推奨されます。これは,炭水化物を摂取するとインスリンが分泌され,それが脂肪組織における脂肪分解を抑制してしまうためです。すなわち,脂肪を効率的に利用しようとすることを妨げてしまいます。トレーニング開始時には血糖値が正常の状態(高過ぎもなく,低過ぎもない)であることが望まれます。
Train-Low, Compete-High戦略
この戦略は,炭水化物の摂取量を調整することで,持久力向上を目指すというものです。特に体に蓄えられている炭水化物(グリコーゲン)について,それが低い状態でトレーニングを行い(Train-Low),高い状態でレースに挑む(Compete-High)というものです。
グリコーゲン量が少ない状態でトレーニングをすることで,意図的に炭水化物の利用度を低く抑えることができ,ひいては持久力の向上に繋がります。実践的なアプローチの方法としては下記のようなものが示されています。
- 空腹時トレーニング:朝食前の空腹時に低~中強度のトレーニングを行う
- 低グリコーゲントレーニング:毎日1回ではなく,2日ごとに1日2回の運動を断続的に行う
ただし,グリコーゲンが枯渇した状態で運動すると,免疫機能のいくつかの指標に異変が生じるとされています。したがって,このような新しい食事法をためす際には,理想的には栄養の専門家のアドバイスをうけることを検討しましょう。
筆者の場合は,週半ばのスピードセッションや週末のロング走以外はジョグなのですが,そのジョグは早朝に空腹時に行います。筆者のライフスタイルに合わせた方法ですが,持久力向上には向いた戦略であるようです。ただし,ロングジョグでは行っておらず,時間は1時間から長くても1時間30分以内。高強度のポイント練習や,2時間を超えるようなロング走では行わない方が良いでしょう。あくまでトレーニング全体の一部として取り入れる戦略であると言えるかと思います。
ケトジェニックダイエットと高脂肪食
脂肪の利用を向上させるためのアプローチとして,ケトジェニックダイエットがあります。伝統的な方法としては脂質:たんぱく質または脂質:炭水化物のエネルギー比を4:1とするしたり,修正ケトジェニックダイエット(エネルギー摂取の70%を脂肪から)などがあります。脂肪酸化率は確かに向上することが示されていますが,高強度でのパフォーマンス能力は低下する可能性があります。ウルトラマラソンランナーに対する持続的なケトジェニックダイエットのパフォーマンス向上効果を裏付ける文献は不十分であり,さらなる研究が求められています。
その他の補給
たんぱく質サプリメント(プロテイン)
先ほどは「1.6g/kg体重を超えるたんぱく質摂取を推奨」「より多くのエネルギーを必要とする場合には2.5g/kg体重まで正当化される」と説明しました。ただし,食事から必要なたんぱく質を満たすことが難しい場合は,ホエイプロテインなどのサプリメント利用が検討できます。
また,摂取のタイミングについても,起きている時間で,3時間ごとに約20gのたんぱく質を摂取することが,筋たんぱく質合成には良いとされています。
ただし,最近はそこまで摂取のタイミングは重要でない(総量が重要)という論調になっていると思います。
毎日の水分補給ガイドライン
日々の水分補給戦略として,ほとんどの場合,喉の渇きに応じて飲むことで達成できるとされます。ただし,喉の渇きによる感覚は,急性的な脱水に対してのみ適切である可能性があるため,慢性的な脱水状態を防ぐためには,尿の色チャートを活用して監視するなどが推奨されます。
筆者の場合は,喉の渇きを感じにくいのか,集中したりしてると半日飲み物を飲まないなんてこともあるので,近くに飲み物を置いておいて,水分補給までのハードルを最小限にするようにしています。
またトレーニング後の水分補給戦略としては,回復時間が短い場合や水分損失が大きい場合は,喉の渇きに任せた水分摂取だけでは水分バランスを回復させるのに不十分とされます。トレーニング中に失われた体液量(運動前後の体重測定で推定可能)よりも多い量(150%)の体液を摂取することが,水分バランスを完全に回復させるために必要です。
筆者の場合は,トレーニング前後に体重を測定し,減った分をプロテインサプリメントなども含めて可能な限り早めに摂取するようにしています。
【トレーニング編】まとめ
100kmウルトラマラソンを完走するには,レース当日の補給だけでなく,それを受け止める「身体の土台」をトレーニング期から作っておくことが不可欠です。
この記事では,国際スポーツ栄養学会(ISSN)の科学的知見に基づき,トレーニング期の食事戦略を解説しました。
トレーニング期の栄養戦略 ポイント
- エネルギー摂取:トレーニング距離・時間に応じて,十分なエネルギー(目安:35〜55kcal/kg体重)を摂取しましょう。日々の体重や消費エネルギーをモニタリングし,自分に合った量を見つけましょう。
- 炭水化物(エネルギー源): 総エネルギーの約60%(目安:5〜8g/kg体重)を炭水化物から摂取します。高負荷のトレーニング時には最大10g/kg体重まで必要になることもあります。
- たんぱく質(身体の材料): 筋肉の修復と構築のため,体重1kgあたり1.6gを超えるたんぱく質(高負荷時は最大2.5g)が推奨されます。食事だけで難しい場合はサプリメントも有効です。
- 脂肪燃焼効率の向上:ウルトラマラソンでは脂肪を効率よく使う能力が鍵となります。「運動直前の炭水化物摂取を避ける」「空腹時に低強度で走る(Train-Low)」といった戦略は,脂肪燃焼能力を高めるのに役立ちますが,負荷の調整も必要です。
- 水分補給:日常的には喉の渇きや尿の色を目安にします。トレーニング後は,失った体重の150%を目安に水分を補給し,確実に回復させましょう。
次回は【レース編】として,レース当日に「何を」「どれだけ」「どのように」補給すべきか,そして「胃腸トラブル」にどう対処すべきかを詳しく解説します。