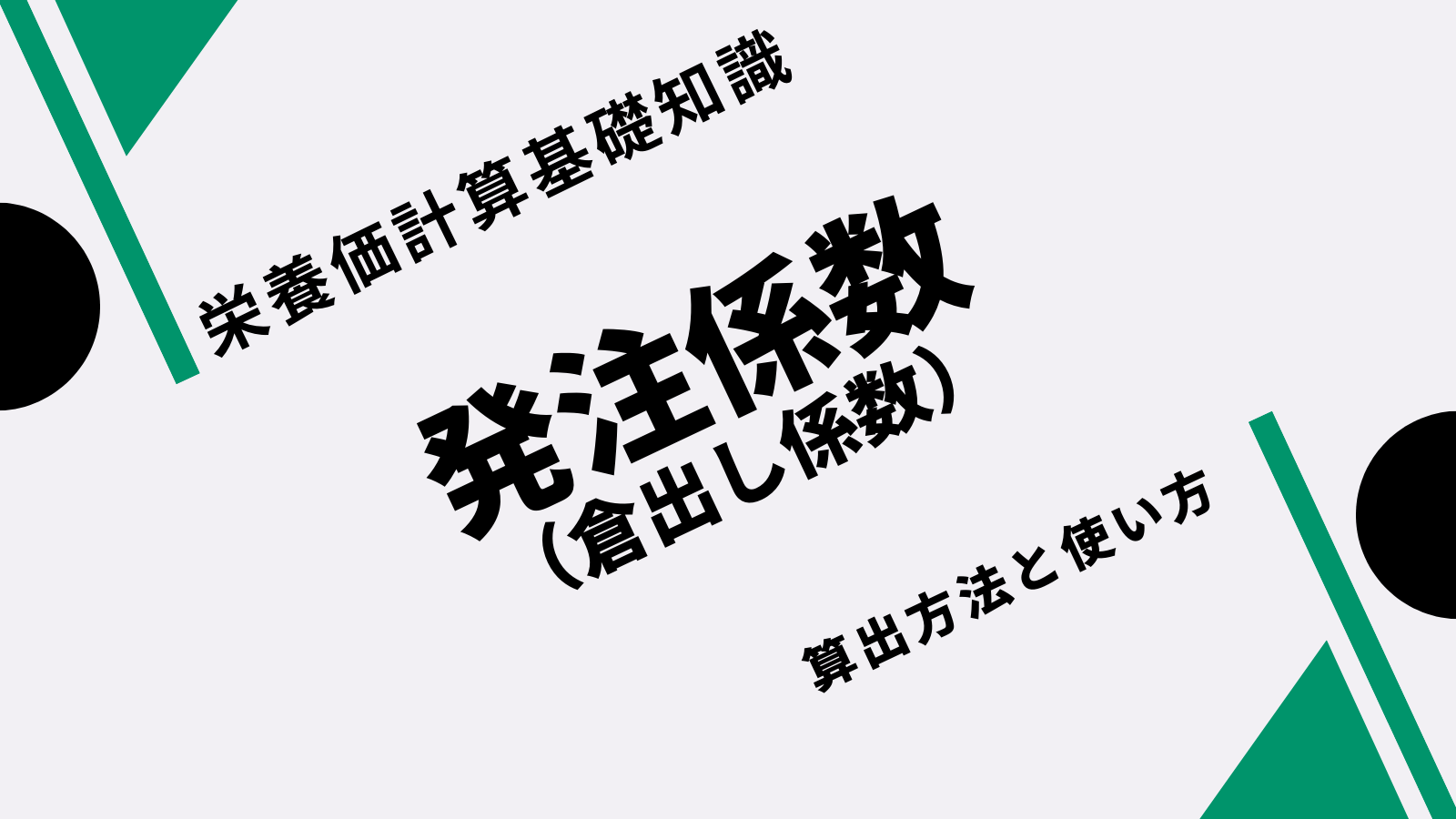みなさん,こんにちは。
シンノユウキ(shinno1993)です。
献立作成や給食管理では,食材の発注量を計算する必要があります。その際に,発注係数(倉出し係数)を使用すると便利です。発注係数は,発注量換算係数とも呼ばれます。
しかし,栄養士・管理栄養士を目指す学生や,着任したばかりの新人の方には,発注係数の算出方法や使用方法がわからないこともあるでしょう。
そこで今回は,発注係数(倉出し係数)の算出方法と使い方について紹介します。
発注係数(倉出し係数)とは?
発注係数(倉出し係数)は,食材の発注の際に使用される係数のことです。これを使用することで,実際に調理に使用する量から,発注する量を簡単に算出できるようになります。
食材には,食べられない部分があります。たとえば,ほうれん草の根っこや,卵の殻です。献立に記載される食材の重量は,実際に食べられる部分だけの重量(可食部重量)であることが多いです。
しかし,実際に食材を注文して納品される際には,食べられない部分も含めた重量で届けられます。そのため,調理の際に廃棄される量を加味し,多めに発注しておく必要があります。この多めに発注する際に利用されるのが,発注係数(倉出し係数)です。
発注係数(倉出し係数)の算出方法
発注係数(倉出し係数)の算出方法は,施設によって異なる場合があります。もし施設独自の算出方法がある場合は,それに従ってください。下記では基本的な算出方法について説明します。
発注係数(倉出し係数)は,以下で算出できます。
可食部率とは,食品のうち食べられる部分の割合です。たとえば、100gの食品のうち,80gが食べられるなら,可食部率は80%です。可食部率については,発注量計算のための「廃棄率」と「可食部率」という記事でも解説していますので,ご覧ください。
計算の例を下記に示してみます。
例)廃棄率が80(%)の場合
発注係数(倉出し係数) = 100(%) ÷ 80(%)
発注係数(倉出し係数) = 1.25
上記のように,可食部率がわかれば,発注係数(倉出し係数)は簡単に計算できます。
発注係数(倉出し係数)の使い方
上記で発注係数(倉出し係数)の算出方法の例を紹介しました。これを使うことで,実際に使用する量(純使用量ともいいます)から,発注する量を計算することができます。基本的な使用方法は下記の通りです。
それでは,純使用量が40g,発注係数が1.25の場合の例を紹介してみます。
例)純使用量が40g,発注係数が1.25の場合
発注量(g)= 40(g) × 1.25
発注量(g)= 50(g)
発注係数がわかれば,純使用量に掛けるだけで,発注量を簡単に計算できます。食品ごとに発注係数を算出しておくと,とても便利です。
まとめ
今回は,発注係数(倉出し係数)の算出方法と使い方について紹介しました。難しそうな言葉に聞こえたかもしれませんが,特段難しいものではありません。
難しい点といえば,(途中でも紹介しましたが)可食部率についてかもしれません。これについては,別記事で詳しく紹介していますので,参考にしてくださいね。