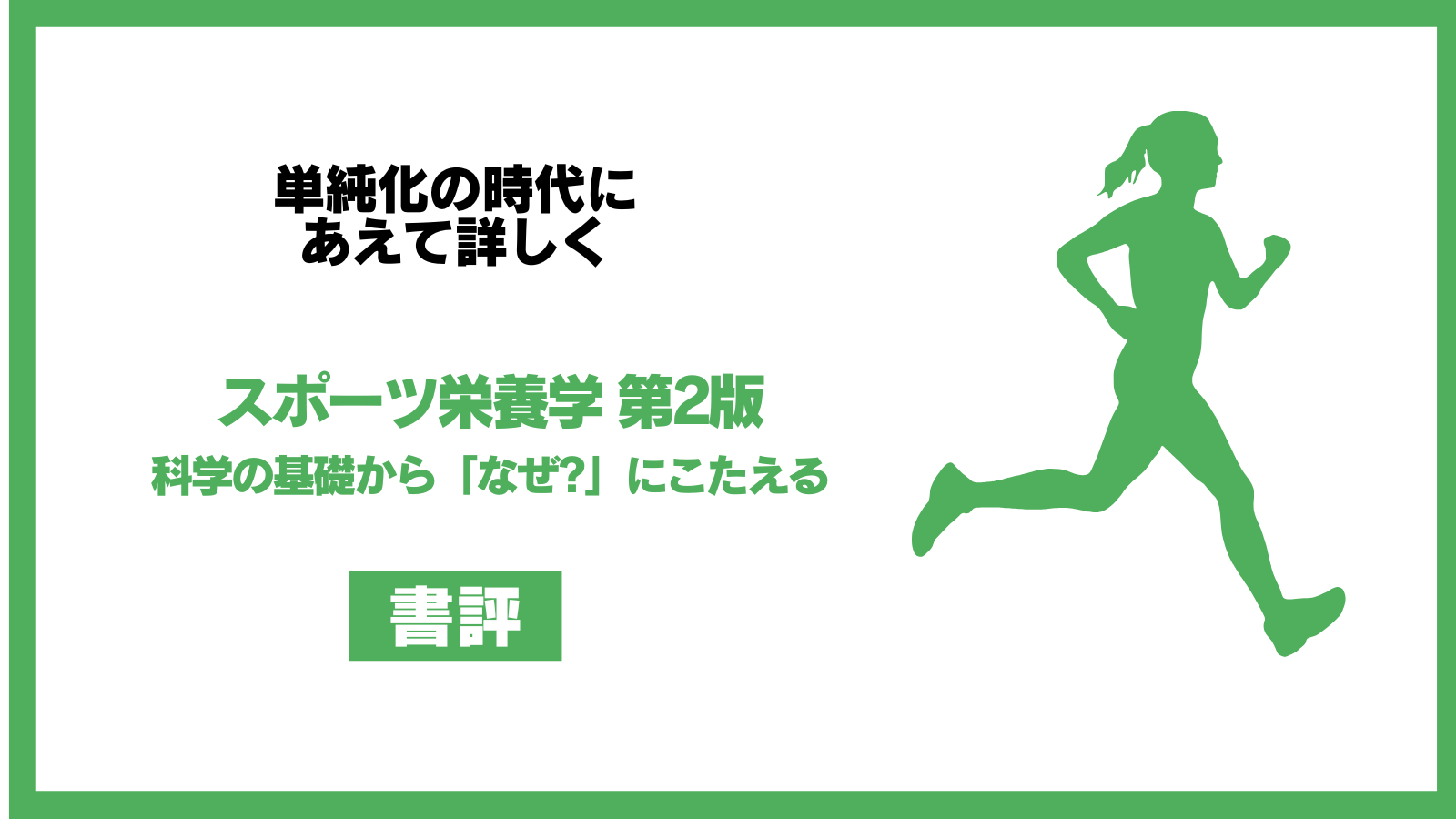みなさん,こんにちは。
シンノユウキ(shinno1993)です。
今回はスポーツ栄養学についての書籍『スポーツ栄養学 第2版: 科学の基礎から「なぜ?」にこたえる』を紹介します。
本書は,スポーツ栄養学についての専門書に位置づけられる書籍です。そのため,書店さんのスポーツコーナーに並んでいるような,食事の写真やイラストがふんだんに使われている書籍(実用書)と比べると,やや取っつきづらさを覚えるかもしれません(上記のリンクから紙面見本を見てもらうと分かるかもしれませんが,白黒ですし文章が主体です)。しかし,だからこそ,あえて“難しい”本書をオススメしたいと思っています。特に,私と同じスポーツ栄養を学んでみたい栄養士・管理栄養士は,ぜひ本書を読んでみてください。
本書の立ち位置と狙い
上記でも紹介しましたが,本書はハウツー本ではなく,理論とメカニズムに寄った本です。そのため,本書の「はじめに」にもあるように,「各種スポーツ活動をサポートするためにはどのような食事を準備すべきなのか」といった問いを即座に解決するものではありません。そのため,実用書には付き物である献立の例なんかも載っていません。ここからさらに一歩踏み込んで「なぜそのように摂取すると効果的なのか?」というメカニズムを細胞レベル・分子レベルで解説しています。
とはいえ,普段の食生活に反映できるような“即効性のある”内容はないのかというと,そうではないと思っています。私はマラソンを趣味にしており,ほぼ毎日ランニングをし,レースに向けてトレーニングを積んでいます。アスリートレベルではなくアマチュアの市民ランナーレベルでしかなく恐縮なのですが,私は本書の内容の一部を食生活に取り入れてみようと考えています。
具体的には,「5.4 脂質摂取とパフォーマンス」のところです。これを読み,「マイルドファットアダプテーション(中程度脂質食)」に興味を惹かれました。私は42.195kmを走るフルマラソンに加え,それ以上の距離を走るウルトラマラソンにも挑戦しています。そういった長距離種目では,走る際のエネルギー限として,脂質を活用することが重要になってきます。炭水化物の割合を極端に制限するケトン食には挑戦しきれなかった私ですが,中程度の脂質食であれば丁度良いあんばいかもしれないと思い,取り入れてみようと思っています。
糖質と脂質どちらを利用したほうが有利となるかは,それぞれの競技特性によって異なるため,その競技特性に適した糖質と脂質の摂取比率を検討しなければならない。(中略)高糖質食と高脂質食にともなうメリットとデメリットをよく理解したうえで,まずはどのような糖質と脂質の摂取比率が自分の競技および自分の体質にとって最適なのか,ということを実際にいろいろと試しながら検討する必要があるだろう。
寺田新 著『スポーツ栄養学 第2版: 科学の基礎から「なぜ?」にこたえる』, p.303東京大学出版会, 2024.
さまざまな食情報を自分で活用できるように
本書は「食情報」についても,とても示唆にとんだ内容を含んでいます。
たとえば「コラム6 トップアスリートの経験談」には,下記のような内容があります。
近年,多くのトップアスリートが,ソーシャルネットワークサービス(SNS)などを通じて,さまざまな情報を発信しており,自身が行っている食事法やトレーニング法などを公開するケースも多く見られる。そのようなトップアスリートの経験談を見た一般の運動愛好家やジュニア選手のなかには,その手法を真似して,実際に取り入れてみようとする人たちもいる。はたして,トップアスリートが用いている手法は,そのような人たちにとっても有効なものとなりうるのであろうか?
寺田新 著『スポーツ栄養学 第2版: 科学の基礎から「なぜ?」にこたえる』, p.308東京大学出版会, 2024.
なかなか刺さる内容です。私自身,ウルトラマラソンのトップアスリートがケトン食を取り入れていることを知り,導入することをとても前向きに検討しました。色々と調べるとパフォーマンスへのメリットとデメリットがあることを知りました。しかし,それらがなぜ生じるのかは,あまり触れられていませんでした。本書を読むと,それを理解するために必要なメカニズム主体の知識も得られます。
食情報は,スポーツ栄養に限らず,色々とあふれています。本書を読むことは,それらを理解・解釈し,適切に活用するための助けになると思います。